FinancialAdviser1月号の 「つみたてNISAを活かした資産形成アドバイス」特集で、つみたてNISAの活用方法について原稿を書かせていただいています。
ファイナンシャルプランナー(FP)や銀行などの金融機関の職員に読まれている雑誌なので、一般の方は目にする機会は無いかもしれませんね。

その中では6人のFPがそれぞれつみたてNISAの活用法を書いていますが、多くのFPが個人型確定拠出年金(イデコ)と違って、つみたてNISAのいつでも引き出せる点を大きなメリットとして挙げています。
いざという時に引き出すことができる安心感
やはりイデコの原則60歳まで引き出せない点は、ライフプランを考えれば大きなリスクになります。
住宅資金や教育資金などで急に資金が必要になっても、イデコで貯めている資金は使えませんからね。
奨学金を借りている学生の割合が過半数を超えている世の中の現状を踏まえれば、FPとしてそう簡単にイデコの利用を勧めることはできません。
その一方で、つみたてNISAで貯めた資金はいつでも引き出すことができます。
投資信託なので預貯金のように即日引き出せるわけではありませんが、休日を含めても1週間前後で引き出せるようになります(換金まで4~5営業日とされていることが多い)。
解約してしまうと長期に渡る資産形成効果を損なってしまうことにつながりますが、それでもいざという時に引き出すことができることは、やはり安心感につながってくるでしょう。

ノーロードなので解約しても販売手数料コストが気にならない
また、つみたてNISAの商品は全て販売手数料がゼロ(ノーロード)になっているので、途中で解約しても購入当初のコスト負担が大きく投資収益の足を引っ張ることもありません。
それはどういうことかというと、例えば銀行や証券会社の窓口で販売されている投資信託の場合、販売手数料が2%~3%前後かかるものが多いですが、例えば3%(プラス消費税)の場合、5年で解約したとすると1年あたり0.648%、10年で解約する場合でも1年あたり0.324%のコストがかかることになります。
しかし、つみたてNISAはこのような販売手数料がかからないので、20年の非課税期間が終わる前に解約をする場合でも、販売手数料のコスト負担を気にしないでいいのです。
もちろん途中で解約しても運用益は非課税です。

あくまでも老後に向けた資産形成手段という考えで
だからといって、途中で解約することを前提につみたてNISAを勧めたいわけではありません。
積立の途中で解約をしてしまうと複利による資産形成効果が発揮されにくいので、その分運用益が非課税になるメリットを活かしにくくなります。
つみたてNISAの本来の趣旨は、将来的に年金財政が厳しくなっていくことが予想される中で、国民の自助努力による老後資金準備を税制面で優遇して促していこうとするものです。
購入方法を定時定額購入(いわゆる積立)に限定し、対象ファンドを信託契約期間が無期限または20年以上、分配頻度が毎月でないこと等を条件にしているのは、あくまでも老後に向けた資産形成手段としての合理性を考えた上での制度だからです。
しっかりとライフプランを考えて、キャッシュフロー表(収支シミュレーション)で今後の家計の収支状況を確認してから、つみたてNISAの活用を考えることが大切であることは覚えておいてくださいね。
久保 逸郎
最新記事 by 久保 逸郎 (全て見る)
- 【過去10年の運用実績で検証】 本当にアクティブファンドの多くは、パッシブ運用(ETF、インデックスファンド)に劣るのか? - 2021年6月22日
- 自営業者の老後資金準備で最もおすすめの方法とは~小規模企業共済・国民年金基金・個人型確定拠出年金~ - 2021年3月4日
- 豊かな老後を過ごすために知っておきたい、リバースモーゲージのメリット・デメリット - 2021年2月13日
- 債券投資を行う時に、投資先の信用力の確認を怠ってはいけない - 2021年1月16日
- 仕事としての運用と、趣味の運用は分けて考える - 2020年12月16日






















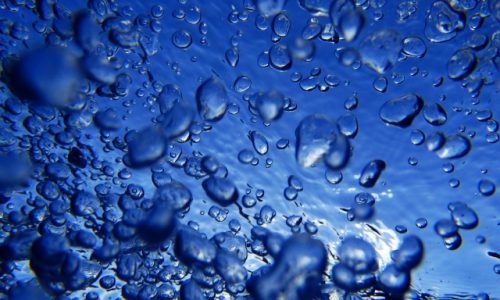
この記事へのコメントはありません。